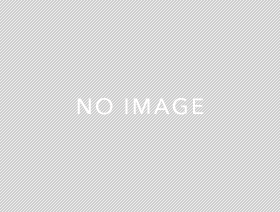体型で性格がわかるってホント?ちょっと昔の心理学

戦前に流行っていた心理学
1920年代では体型を3つの種類に分けて人の性格が分類できるということが信じられていました。今も話自体は残っていて、どこかで聞いたことある方もいるかもしれません。
現在の心理学では「人の体型などで性格をきちんと分析することはできない」という考えが主流です。そのため、こうした性格分析の話は昔話という程度の認識です。
そうはいってもこういう体型の人にはこういう人が多いという臨床的な統計に基づいた説でもあるので、そのデータ自体をあながち否定できるものでもありません。こうした話が飛躍して、こういう体型だから○○なやつだという誤解が先にはびこって、反証の結果が積み重なりこの説は否定されたという見方もできるでしょう。
では、なぜこうした学説が広く認識されて、今でも心理学という皮を被って、世の中にひろがっているのでしょうか。実はそれには心理学を使って説明できる理由があるのです。その説明をするためにも、体型の分析についての2つの学説をご紹介します。
クレッチマーの気質3類型
クレッチマーは1920年代のドイツの精神科医です。先程申し上げたとおり、人の体格と人の性格が分類できるのではないかと考えて、こうした3つの分類にまとめました。
内閉性性格
非常に痩せた人の性格。自分の世界に閉じこもりがちで非社交的。非現実的でもあり、気難しい学者のようなタイプ
循環性性格
肥満型体型の人の性格。躁状態とうつ状態が交互に現れて、陽気で社交的。世話好きで高笑いをする社長のようなタイプ
粘着性性格
がっちりとした筋肉質の体型の人の性格。几帳面で真面目だけど頑固な一面も。権威主義で、上に弱くて、下に強く当たってしまう。
ひょっとしたらここまでで、何人か該当する人が頭に浮かんでいるかもしれませんね。この分類によってかかる精神疾患が違うとも言われています。
シェルドンの性格3類型
上のクレッチマーの分類法に加えて、独自に調査を加えてまとめたのがアメリカのシェルドンです。
頭脳緊張型
痩せ型の人の傾向。大脳の動きが活発で神経が繊細。繊細で疲れやすく、他人に対しても神経を使うため、人前に出るのを好まない。
内蔵緊張型
暇型の体型の人の傾向。消化器系を中心に内臓機能が活発。落ち着きが合って、感情的だが、温かみがあって人付き合いが活発。
身体緊張型
筋肉質の人の傾向。エネルギッシュで行動的。常に目標を目指して行動していて、多少の忍耐は気にならない。競争心が旺盛。
シェルドンのほうは精神疾患を持っていない人たちの統計に重点を置いています。そのため、病的な要素は少なく、男女の相性もこの理論で説明しています。
言われなくても、どこか知っていたような話である気がしませんか?筋肉質の人が繊細で学者的というのも想像しにくいですし、逆も又然りです。もちろん、そういう人がいないということを言いたいわけではなありません。
人は見たいように見る
見た目と内面が違っているなんていうことは非常によくあります。もちろん、ピッタリということもよくあります。問題はなぜ見る側が相手を何かの型にあてはめて見ているのでしょうか。
それは人はいろんな経験を元に見たいように見て、聞きたいように聞いて、感じたいように感じているからです。子供の頃はいろんなものが新鮮で前もった情報がありません。そのため、見るものすべてが初めての映像であったり、新鮮なものです。しかし、大人になってしまうと、それだけ多くのものを見ているので今までの経験値で物事を見てしまいます。
泣くから悲しいのか、悲しいから泣いたのか、という問題があります。にわとりが先か卵が先かのような問題ではありますが、実はわかっているようで自分のことすらわかっていないのです。
相手が痩せていて、ちょっとトゲトゲしていそうだから相手がトゲトゲしているのか、相手がトゲトゲしていたから、ますます痩せているように見えているのか、表裏一体の問題なのです。少なからず、上の分類は当たっていることがあります。占いと一緒でそれだけ多くの統計をとっていればそういった傾向があることは統計的に事実でもあるのでしょう。
しかし、原因と結果を重視する学問というフィールドではそれは一節として認めるわけにもいきません。反証はたくさんあります。
私たちができるのは、その人のその姿をちゃんと見てあげることです。今までのデータの中にきっとその人そのものはいません。どんなに分析したってそれはその人を構成しません。心理学、生理学、いろんな学問で切り取ってもそれはその人を構成しません。意外とそのことを忘れてしまって人を名詞で判断しようとする人がたくさんいます。名詞で判断されて、カテゴライズされる側の気持ちになってみればそれがどうも違うというのはなんとなく感じるでしょう。
会社の中でも、その人を他で当てはめられた名詞で判断するのではなく、その人個人だと思って、いろんなことを観察してみることでその人が精神疾患であるかどうかというのは実はそこまで関係がないことなのかもしれないと思えてくることでしょう。
いろいろな人がいることを大事にするという多様性(ダイバシティー)の一環として、メンタルヘルスケアだけでなく、職場の中でもいろんな人がいることを考えてみることで本当によい職場づくりができるのではないでしょうか。