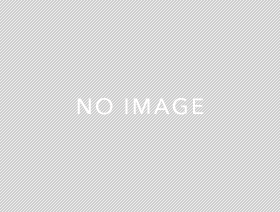うつ病の人との接し方

うつ病になってしまった大切な人との接し方
 大切な人。今まで家族、仲間として日常を共にしてきた人がうつ病になると突然気持ちが通わなくなります。うつ病になってしまった本人は自分自身に混乱し、状況を上手に伝えることができなくなります。周囲の人に「こうやって接して欲しい」と上手に伝えられないのです。そして、多くの場合、周囲の人もうつ病を理解しきれず、「どうやって接して良いかわからない」となってしまいます。
大切な人。今まで家族、仲間として日常を共にしてきた人がうつ病になると突然気持ちが通わなくなります。うつ病になってしまった本人は自分自身に混乱し、状況を上手に伝えることができなくなります。周囲の人に「こうやって接して欲しい」と上手に伝えられないのです。そして、多くの場合、周囲の人もうつ病を理解しきれず、「どうやって接して良いかわからない」となってしまいます。
お互いに「助けたい」「助けて欲しい」と思っているのに心が通わず、場合によっては知らない間に傷つけてしまったりすることはぜひ避けたいものです。このページでは「うつ病体験者の声」「カウンセラーの声」などの現場での実際の事例を交えながらうつ病になってしまった大切な人との接し方をお伝えします。ぜひこの記事を大切な人との接し方に役立ててください。
うつ病の人を苦しめる接し方
うつ病の症状が重かったり、不安定な時には次のような接し方をしないように気をつけてください。多くの場合、次のような接し方をすることでうつ病の症状を悪化させたり、必要以上にその人を傷つけてしまうことになります。
理解されないことが最もつらい
うつ病の人が他の人と関わる時に最もつらいのが「理解されないこと」です。一見すると大丈夫そうに見えたり、自分にも同じような経験があると安易に言われてしまうと「ああ、理解されないんだ」とうつ病の人は心を閉ざしてしまいます。
うつ病の実例
うつ病になると朝がつらい。「もう寝るしかない」と思えるほど体が重く、気持ちも塞いでしまっている。それなのに家族は「よく寝られた?少しは元気になった?」と期待を込めて聞いてくる。「ああ、うん」と答えるしかない。うつ病を味わったことがない人は寝て起きたら体調が悪くなっているなんて想像もつかないのかもしれない。
うつ病を軽視する接し方
うつ病の人を元気づけようと当事者ではない人の発想で説得しようとする人もいます。「世界には食べ物もなくて困っている人もいるんだよ」のようにうつ病を軽視するような言葉がけをされるとうつ病の人は酷く傷つきます。「理解したつもりになって説得する」これは非常に危険なアプローチと言えます。
うつ病の事例
ある高齢の精神科に「戦争をしている最中にうつ病になる人はいなかった」「君ね!戦場でうつ病になったら撃たれて死ぬんだよ」と言われて愕然としました。だったら、僕を撃ち殺して欲しい。そうすればうつ病から解放されるから。
感情をぶつけるような接し方
 うつ病の人と関わっている家族や同僚、友人にも非常に大きなストレスがかかります。「いつまでダラダラしているんだ!」「いい加減にしろ!」とつい感情的になって接してしまうのもわからなくはありません。しかし、そんな感情をぶつけられた人は余計に自分の存在意義を見つけられなくなり、うつ病の症状を悪化させてしまいます。多くの人が唯一の居場所であるはずの家庭で感情的なぶつかり合いをきっかけに居場所を失ってしまいます。最後の居場所を失った気持ちは「死んでしまおうか」という気持ちにつながりやすくなってしまうので非常に危険です。
うつ病の人と関わっている家族や同僚、友人にも非常に大きなストレスがかかります。「いつまでダラダラしているんだ!」「いい加減にしろ!」とつい感情的になって接してしまうのもわからなくはありません。しかし、そんな感情をぶつけられた人は余計に自分の存在意義を見つけられなくなり、うつ病の症状を悪化させてしまいます。多くの人が唯一の居場所であるはずの家庭で感情的なぶつかり合いをきっかけに居場所を失ってしまいます。最後の居場所を失った気持ちは「死んでしまおうか」という気持ちにつながりやすくなってしまうので非常に危険です。
うつ病の事例
「お前は我が家のお荷物だ!」家族からそう言われました。いつか来るなとは感じていましたがいよいよ言われてしまったか!この世に居場所がなくなったんだなと寂しいような冷めたような気持ちになったのを覚えています。
「頑張れ」という言葉がなぜ悪いか?
うつ病の人に「頑張れ」「頑張って」って言っちゃいけないとよく言われます。それはすでに死ぬ思いで頑張っているので「頑張って」という言葉がけが「頑張っていない」という意味合いになってしまうからです。でも、うつ病の人は「頑張って」と言って接して欲しい時もあります。正確に言うと「頑張って」と言って欲しくない人と言って欲しい人に分かれるのです。つまり、「頑張れ」「頑張って」というセリフが悪いのではなく、理解がない人に言われる「頑張って」がうつ病の人を傷つけるのです。
うつ病の事例
うつ病経験が8年もあるのに今はとても楽しく、満たされた人生を送っている人に会いました。「ああ、自分のうつ病から抜けてこの人みたいになりたいな」と思う体験でした。その人は自分自身の闘病経験を語りながらも私のうつ病のつらさをしっかりと受け止めてくれました。「ああ、それはつらかったね」という言葉が私の心に刺さりました。「ああ、理解してもらえた」そして、「僕もなんとかこうしてしあわせになれた。協力するから頑張ろう!」と励まされたことは絶望の淵に救いの手が差し伸べられたような、力が湧いてくるような体験でした。「この人について、もう一度このうつ病の淵を登って脱出を試みよう」そう思いました。
否定されたと感じてしまうこと
周囲でサポートする人にその気がなくてもうつ病の当事者にとっては「否定された」と感じてしまうような話題、メッセージはたくさんあります。うつ病がなかったら気にもしないことで傷ついてしまうこともあるのです。100%それを察することは難しいですが、できる限り注意して接するように心がけてください。
うつ病の事例
太陽の光が窓の外に感じられると「みんなは働いているんだな」と感じ、自己否定的な気持ちに襲われました。わかっていても時間を感じるのがつらい。あまりにつらいので母に遮光のカーテンを買ってもらい、部屋を真っ暗にしました。本当の真っ暗闇の中だと少しだけ安心できるのです。
うつ病の人の助けになる接し方
一方でうつ病の人の助けになる接し方もあります。うつ病の人はコンディションや時間帯などによって気分が変わったり、状況が変わるので周囲から見ると理解しにくい存在だと言えますが、理解できるまで1時間でも3時間でも耳を傾けようとして話を聞いてもらえると徐々にその言葉にしにくい状況を伝えられるようになってきます。ここではうつ病の人の助けになる接し方をお伝えします。
じっくり向き合ってもえる時間があること
うつ病の状態は簡単に説明できるものではありません。また、いつでも説明できるというわけでもありません。しかし、時折、状況を話せそうなタイミングがやってきます。そんな時に「否定」「批判」「評価」しないでただただ話を聞いてくれる人がいるとゆっくりと状況を話すことができます。聞いてもらえたこと。少しだけでも理解してもらえたこと。何よりも自分に向き合ってくれる人がいることがうつ病の症状を和らげてくれます。
カウンセラーの心構え
うつ病の人のカウンセリングをする時には時計をうつ病の方の真後ろに設置します。そうすることで大きく目を動かさなくても時間を確認することができます。雑用や時間に気をとられることなく、100%その人に集中することがうつ病の人と向き合う時には重要です。その位置にある時計を見る時にも「そんな時にはどんな気持ちになりますか?」のようなやや考えないと答えられないような質問を投げかけて、うつ病の方が下を向いたりしたスキに時計を確認するくらいの配慮をします。うつ病の人への接し方のコツだと思います。
声の大きさ・テンポをあわせる
元気な状態ならばあまり気にならない声の大きさの違いや話すテンポの違いに注意します。必要以上に大きな声やハキハキしすぎな声で話しかけるとうつ病の人は疲れてしまいます。基本は相手の声に合わせて、やや小さめでゆっくりと話をします。ただし、うつ病の人との接し方に慣れてきて関係性ができてきてからは声を大きくしたり、ややアップテンポにすることで場の空気を徐々に変えていくこともできます。プロのカウンセラーは60分かけて声を変化させ、うつ病の人が知らず知らずのうちに早口で叫んでしまうような促し方をすることもあります。
うつ病体験者の接し方が教科書
うつ病当事者に対してはうつ病の体験者が話しかけることが王道といえます。「私も体験があるんだ。僕の場合には◯◯だったから、全く同じ状況ではないけれども、理解されなかったし、先が見えなくて辛かったのを覚えているよ」のように一言言われるだけでうつ病の人は心を開きます。もちろんこれは実体験に基づいているからこそできる接し方と言えますが、うつ病の家族、うつ病の友人と関わった経験を実体験に基づいて話すだけでもうつ病の人が心を開いてくれる確率は上がります。
うつ病の事例
あるカウンセラーさんの紹介でうつ病を克服した人とお話をしました。話せば話すほどその人の方がつらかったんじゃないかと思うような話でした。本人の実体験を話しているのでそれが僕の魂にビリビリと響きました。その人があまりに明るく、幸せそうなので僕は羨ましく思いました。その後、そのカウンセラーさんは合計で10名のうつ病を克服した人を紹介してくれました。それぞれが違うエピソードを語りながら、幸せそうな顔をするので「うつ病が治らない」というイメージをもてなくなりました。元当事者と接することのパワーは計り知れないと思います。
うつ病の人への接し方(ケーススタディ)
うつ病の人が閉じていて話したがらない時
うつ病の人と接する時に気をつけたいのがタイミングです。どんなに約束をしていたからといって、どんなに客観的に今がちょうど良いと思っても本人の心身のタイミングが「今じゃない」と感じたら話をするのは非常に困難です。「話したい」というタイミングが来たらいつでも声をかけてね!と伝えておくことでタイミングの主導権を渡してしまうことが接し方のコツといえます。
職場でうつ病の人と関わる時
 よほど近い距離にいる人以外は「私はうつ病のことを気にしていますよ」というサインが出ないような接し方がオススメです。「うつ病なんだって?大丈夫?」という空気は余計に相手を落ち込ませてしまいますし、うつ病を余計に意識させることになってしまいます。関わりが非常に強い人を除いてはうつ病などないかのように接してください。ただし、直属の上司や同僚で関係性が強い場合には「今日は暑いね」のような雑談をたまにしてあげることでネガティブなスバイラルを止めてあげることもできます。重要な話。重い話。ではなく、日常的な話を中心に様子を見ながら関わりを持ってください。
よほど近い距離にいる人以外は「私はうつ病のことを気にしていますよ」というサインが出ないような接し方がオススメです。「うつ病なんだって?大丈夫?」という空気は余計に相手を落ち込ませてしまいますし、うつ病を余計に意識させることになってしまいます。関わりが非常に強い人を除いてはうつ病などないかのように接してください。ただし、直属の上司や同僚で関係性が強い場合には「今日は暑いね」のような雑談をたまにしてあげることでネガティブなスバイラルを止めてあげることもできます。重要な話。重い話。ではなく、日常的な話を中心に様子を見ながら関わりを持ってください。
関わる人が倒れないように
家族や同僚など関わる側の人にも大きな負担になるのがうつ病です。一人で対応しようとせずに専門家を交えることが大事です。また、元当事者など自然にうつ病の方と話ができるスタッフをメンタルケア担当者として育成しておくことができるとフォローをする側がとても楽になります。うつ病の方は自分のせいで誰かが落ち込んだり、倒れてしまうことでも傷ついてしまうことがあります。関わる人が倒れない方法を探したり、場合によっては手抜きをすることも重要です。