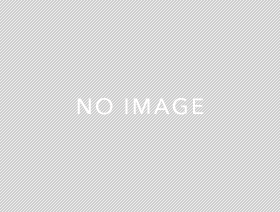働きやすい会社を作る上で考えてほしいこと

働きやすい会社は誰のため?
ゆとり世代はストレス耐性がなく、人間関係が苦手と言われています。その原因は幼い頃から競争することなく横並びで順位をつけられないように育ってきたのがあげられています。ゆとり教育で順位をつけない教育をしようとは定義づけられていなかった気はするのですが、結果としてストレス耐性が弱く、自分で考えて行動できない人が増えてしまっています。
そのような新入社員が増えている一方で働き方の変革を昨年くらいから政府が強く言うようになってきました。女性の社会進出に伴う育児の問題や残業時間の問題、介護離職の問題、メンタルヘルスの問題、労働人口の現象など年齢や家族形態など人生のフェーズに沿ったいろいろな課題が注目されています。
そこで注目されているのが働きやすい会社です。
しかし、それぞれの問題に合わせて、一つ一つ対応していっていると会社の経営どころでは立ち行かなくなってしまいます。さらに、困っている人がいるからなんとかしないといけないという姿勢がチラホラと見え隠れします。
特別さきほどあげた問題のどれにも引っかかっていない人からすると、困っている人に都合の良い休職制度などを作って、手厚く給料を支払ってしまうのを見るとどうしても不公平感が拭えません。
そこで改めて考えてほしいのが働きやすい会社とは誰にとってかということです。
弱い人のための制度はうまくいきづらい
働きやすい会社という定義は人によって様々であるのは確かです。困っている人がいて、その人のために何か援助してあげる制度がたくさんある会社というのは表面的にはかなり働きやすそうな会社です。
メンタルヘルスケアのためにカウンセラーが常備していて、融通の効く勤務時間、育児休暇はたくさんとれる。
たしかにどれの制度もあると嬉しいものばかりです。問題はその制度の意図が困ってる人を助けようとして出来た制度かみんなが働きやすいようにという意識から生まれた制度なのかということです。
困っている人を助けようとする制度はどうしても困っている人を見つけてしまい、困っている人をどんどん増やしていってしまいます。
うつ病の人のためにうつ病にならないようにうつ病の研修とうつ病対策制度と休職制度
聞いているだけで鬱々としてきてしまいますね。心当たりがない人でも、うつのような気がしてきてしまいそうです。そんな制度が育児や介護にもそれぞれあって、介護疲れにならないための研修、介護が必要な人はいませんか?お子さんの具合はどうですか?熱はありませんか?休んでもいいのですよ?
さすがにここまでやる会社はないと思いますがうんざりしてきますね。そして、どうしてもこういう制度は弱っている人を囲って助けるという文脈なので、弱っている人は弱ったままで助けがないと生きていけないどんどんダメな体質になっていってしまいます。
みんなが活躍しやすい会社=働きやすい会社
いろんな事情で企業にとって都合が悪くなった社員は切り捨ててきたのが今までの会社でした。社会がこれだけ多様化していくるとその人個人の事情も価値観もかなり多様になっています。
そんな時代において、働きやすい会社というのは普通の人が普通以上に働ける、少し事情がある人でもそんな人の能力をフルに発揮できる仕組みがある、社員一人ひとりがきちんと活躍できる会社なのではないでしょうか。
メンタルヘルスケアは救済措置ではない
メンタルヘルスケアなんて必要が無いという声も聞きます。しかし、実際にメンタルヘルスケアの現場でやっていることは弱っている人を支える活動というよりも会社全体で社員一人一人が今まで以上にイキイキと働けるようになる仕組みづくりです。弱った人だけを支えればいいメンタルヘルスケアというのは先程申し上げたようなうんざりするようなメンタルヘルスケアで、会社の中でやるにはいささかボランティア精神に溢れすぎています。
介護の世界、教育の世界いろんな業界においても助けてあげないといけないという姿勢では、ほんとうの意味で世の中は働きやすい、生活しやすい社会にはなっていきません。
ピアカウンセラーというのも、うつ病やパニック障害などの精神疾患の人が経験者だからこそわかる活躍の場として機能しています。そこには弱っている人だから助けようという意味は含まれていません。
どんな人にでも活躍できる場があって、存在している意味があるという姿勢で行われている活動です。
働きやすい会社を考える上で、いろんな制度がありますが困った人を助けるためという視点ではなく、世界中のどんな人が来ても普通以上に活躍できる制度づくりという視点でいろんな取り組みをしてほしいと思います。